概要: 2014年に読んだ新刊ベストです。
ベスト◯◯形式って毎年やってると飽きるもので、年ごとに野球やサッカーのベストオーダー形式にしたり目先を変えているんですがどうもしっくりこない。今年、今年はね、長谷川町蔵がこんなことを言っていたので、映画賞形式を試してみることにします。☆のついた作品がベスト・オブ・ベストってことで。
対象: 2013年11月〜2014年12月までの期間に出版された書籍、公開された映画
[ベスト長編]
☆イアン・マキューアン『甘美なる作戦』(新潮クレスト・ブックス)
ド傑作その一。知的で嫌味な諧謔がハマったときの英国小説ほど痛快さは比類なく、マキューアンの近作は間違いなくその部類。『ソーラー』に続いて「おっさんが若い女性に送る古典的な視線」を(たぶん)自覚的に逆手に取った小説であるともいえたりもします。
・ホセ・ドノソ『別荘』(現代企画室)
ド傑作その二。開始二ページで傑作を予感してしまう小説はたいてい尻すぼみに終わりますが、開始二ページで傑作を確信できてしまう小説は、ラスト二ページまで余すところなく傑作であることが多いのです。チリの高貴な一族の方々が、別荘で余暇を過ごすうちに倦怠極まってきて、三十三人*1の子どもたちを置いてけぼりにしてピクニックにでかける、というお話。まあ、端的に言えばラテンアメリカ版『蝿の王』みたいな*2。キャラごとにエピソードが積まれていく群像劇なんですけれど、とにかく出てくるキャラ出てくるエピソードみんなヤバい。主人公(?)格の少年からして母親の溺愛のあまり女装させられて育った子で、それが大人たちがいなくなった途端に断髪して服を着替え、他の子どもたちに革命を宣言するという策士キャラ。仮に魔王の御前にひきずりだされて「儂に一冊、面白い新刊を勧めろ! おもしろくなかったら殺す」と迫られたらまずこれを推します。
・ジョエル・ディケール『ハリー・クバート事件』(東京創元社)
去年の新刊は『プリムローズ・レーンの男』とか『駄作』とか、「書けない作家」が主人公の話が多かった気がする。これは書けない作家が、少女殺しの汚名を着せられた大作家である師匠を助けるためにがんばって真相を探る話。こいつもまたキャラ立ちの勝利である気がします。
・ヘレン・マクロイ『逃げる幻』(創元推理文庫)
なんだっけ。そうそう、ガキが行方不明になったんで探す話。そこそこ頑張れるけどひとつ及ばない部下の前に現れて颯爽と事件を解決する軍人探偵はかっこいい。
・ダニエル・フリードマン『もう年はとれない』(創元推理文庫)
元刑事のクソジジイがナチハンティングする話。作中で「『ダーティ・ハリー』のモデルになったのはおれ」発言があるとおり、クリント・イーストウッドにあてがきしたかのよう。けど、やっぱりジジイなのでアクションしても、ちょっとぶつけただけですぐアザになっちゃうの。
・ロベルト・アンプエロ『ネルーダ事件』(ハヤカワ・ポケット・ミステリ)
ネルーダという南米では知識人や政治家から麻薬カルテルのボスまでひろく好んで引用されるノーベル賞詩人がおりまして、彼からある医師を探してほしいと頼まれた探偵があっちこっち行き来するうちになんだこの大詩人最低なクソ野郎だな、とおもいはじめる話。南米感。狂騒。熱情。この詩情でシリーズ探偵物だというのが驚きます。『夜のみだらな鳥』の新訳が出るドノソといい、これくしょんが刊行されているボラーニョといい、いま、チリ文学がアツい。
・矢部嵩『〔少女庭国〕』(ハヤカワJコレクション)
説明に困るんだけど、なんだっけ、女の子がいっぱい出てきて……『CUBE』みたいなダンジョンで狩りとか農業やって……やがてみんな死ぬ。いや、死なないのもいます。小川一水の短編を百合化して伸ばしたみたいな長編かな、と思ったらなんだかだんだんだんだん変な方向に転がり出すんですね。無節操なようで秩序があります、野蛮なようで倫理があります。
・トマス・H・クック『ジュリアン・ウェルズの葬られた秘密』(ハヤカワ・ポケット・ミステリ)
ジュリアン・ウェルズさんという作家の自殺の真相をお友達が世界中飛び回って探る話。カバー刷新以降イマイチ元気がなかったクックさんにひさびさのクリーンヒット。まあ毎度おなじみ安心確実おいしいクック・ドゥであることにかわりはないのですけれども、そんないつものクックに、ちょっとスパイ・冒険小説的な要素をブレンドすることで素材の味を際立たせております。
・クリスチアナ・ブランド『領主館の花嫁たち』(東京創元社)
館! 双子! 家庭教師! 呪い! 近親相姦! ザ・ゴシック! 本格原理主義界のクリスティーことブランドさんの遺作です。妄想になりますが、長い作家生活でミステリという枠組に挑戦しつづけた彼女がもうパーペキミステリに勝利したなみたいな気分になってじゃあ次はどんな枠組と喧嘩しよーかとまわりを眺め回したところ、当時既にジャンル化してたいたゴシック小説に目をつけたんだとおもいます。
・ミシェル・ウエルベック『地図と領土』*3(筑摩書房)
人間を馬鹿にしている。
[ベスト短篇・連作短編集]
☆キジ・ジョンスン『霧に橋を架ける』(東京創元社)
レイ・ヴクサヴィッチ、柴田訳ケリー・リンク、松田青子訳カレン・ラッセル、と何かしらアメリカン女流スリップ・ストリームが元気だった2014年ですが、その中でニューフェイスのジョンスンが頭一つ抜けてましたね。蜂たちの川、巨獣が潜む霧の川、喋る犬、物語についての物語、奇想一発から「なんだかよくわからんがいい話」に持っていってくれるのは、短編分野では貴重な才能。その語り口はオーラルですらある。
・ 矢部嵩『魔女の子供はやってこない』*4(角川ホラー文庫)
2014年は矢部嵩の年だった気がします。2015年までに矢部嵩を発見できなかったとしたら、きっと後悔のあまり小説読まなくなってた。twitter に感謝、フォローしきれねえ範囲の本をディグってくれる親愛なるフォロイーたちにマジ感謝。
・ブライアン・エヴンソン『遁走状態』(新潮クレスト・ブックス)
人間の抱える強迫観念や不安を高純度で抽出して培養させた小説には一定の需要があり、私もその需要を担う一人です。
・麻耶雄嵩『さよなら神様』(講談社)
探偵をつきつめると神学へゆきつき、神学をつきつめると愛に果てる、というのは一見シニカルでありながらも、一番真摯なのかもね。
・アンナ・カヴァン『われはラザロ』(文遊社)
人間の抱える強迫観念や不安を高純度で抽出して培養さえた小説には一定の需要があり、カヴァンはその需要をすごくわかりやすい形で満たしてくれる作家です。
・ケリー・リンク『プリティー・モンスターズ』(早川書房)
プリティー(雑)。ふだんのケリー・リンクは twitter でふわふわした面白いことをいうおばさんですが、彼女も小説もおおむねそのスタイルに沿います。読みやすいようでいて意外と読んでて疲れるのは、作家と訳者に共通する資質なんで、割と体力あるときに読まないとキツイかぽね。
・木下古栗『金を払うから素手で殴らせてくれないか』(講談社)
歳とともにかつてあった変な文体へのフェティシズムが減退していく今日この頃ですが、たまに変な日本語が読みたければ佐々木中か矢部嵩か古栗をなめます。みんな死なないでほしい。木下古栗を読んでいると日本語はたしかに美しいかもしれないがそれよりもなによりもまずドラッギーでファニーなんだ!!! とおもわされる。たいして収録数集まってないのになぜ今なのか、という疑問は最後の短編を読めば解けます。
・米澤穂信『満願』(新潮社)
連城にも泡坂にも、なんとなれば米澤にも格別の思い入れはないのですが、作家性を純粋な技術として昇華できるのはある種の怪物性のあらわれではないか、とおもうのです。
[ベスト表紙部門]
・『エウロペアナ:二〇世紀史概説』(白水社エクス・リブリス)

・『三銃士の息子』(ハヤカワ・ポケット・ミステリ)
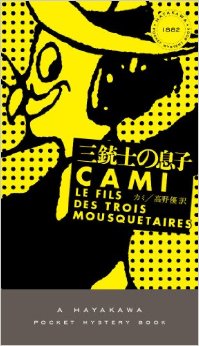
・『狼少女たちの聖ルーシー寮』(河出書房新社)

・『翻訳教育』(河出書房新社)

・『ディープエンド』(論創社)

・『ピース』(国書刊行会)

さいきん、リマスター(何回目だ)されるというFFVIIの画像をみて思ったんですが、あの時期くらいにやたら気合入れて作られたとおぼしき、でも今からするとしょぼくさいCGの質感ってなんかいいですよね。PS2以降にチップチューンを聞かされたときのノスタルジーに近い。/それにしてもカミは装丁に恵まれている。/『ピース』の変な石は『これはペンです』のときみたいな「よくわからないがとてもいい謎の物体」系ですね/『ドリフトグラス』も『ダール・グレン』の白バージョンでとてもおしゃれだったんですが、積んでる。
[主人公部門]
☆セリーナ・フルーム(女スパイ)/(『甘美なる作戦』イアン・マキューアン)
・桑町淳(小五)/(『さよなら神様』麻耶雄嵩)
・マギー(犬)/(『容疑者』ロバート・クレイス)
・高田宏治(脚本家)/(『映画の奈落:北陸代理戦争』伊藤彰彦)
・バック・シャッツ(クソジジイ)/(『もう年はとれない』ダニエル・フリードマン)
[サブキャラ部門]
☆警部(警部)/(『両シチリア連隊』アレクサンダー・レルネット=ホレーニア)
・幽霊の姉弟(近親相姦幽霊)/(『領主館の花嫁たち』クリスチアナ・ブランド)
・ハリー・クバート(ロリコン作家)/(『ハリー・クバート事件』ジョエル・ディケール)
・母親(時間SF母親)/(『SF的な宇宙で安全に暮らすっていうこと』チャールズ・ユウ)
・ハム(胡散臭い保安官)/(『たとえ傾いた世界でも』トム・フランクリン&ベン・アン・フェンリイ)
さんざん無視された末にラストの謎解きにひょっこり現れ推理を披露したあと、自分の身の振り方について唐突な宣言を発する、そんな諦念に満ちたなげやりさがツボ。
全体的に、惨めで幽霊じみてるけどそれなりに強いサブキャラが好きっぽい。
[最優秀短編]*6
☆テッド・チャン「息吹」(『SFマガジン700【海外編】』)
・ブライアン・エヴンソン「マザー・タング」(『遁走状態』)
・キジ・ジョンスン「蜜蜂の川の流れる先で」(『霧に橋を架ける』)
・筒井康隆「科学探偵帆村荘六」(『繁栄の昭和』)
・トム・ジョーンズ「コールド・スナップ」(『コールド・スナップ』)
・木下古栗「IT業界 心の闇」(『金を払うから素手で殴らせてくれないか』)
・ケリー・リンク「墓違い」(『プリティー・モンスターズ』)
・アンナ・カヴァン「わたしの居場所」(『われはラザロ』)
・連城三紀彦「蘭が枯れるまで」(『小さな異邦人』)
・ロベルト・ボラーニョ「鼠警察」(『鼻持ちならないガウチョ』)
・ミネット・ウォルターズ「火口箱」(『養鶏場の殺人/火口箱』)
・ジャック・ケッチャム「シープメドウ・ストーリー」(『狙われた女』)
女王の定員たる12の短編たち。たとえばダイショーの味塩コショウが主人公の小説があるとして、そいつが『虚航船団』の乗組員たちみたいに擬人化された存在ではなく、しんじつ徹頭徹尾ダイショーの味塩コショウとして振る舞うときに、僕らはそれに感情移入し、生き様に感動できるか、と問われれば、ほとんどの人はそんなん不可能だと答えるでしょう。
でも、テッド・チャンにはできるんですよ。そう返せば、これもまたほとんどの人から納得を得られそうな気もする。
[翻訳者部門]
☆舞城王太郎(『コールド・スナップ』)
・池澤夏樹(『古事記』)
・度会圭子&東江一紀(『フラッシュボーイズ』)
・円城塔(『SF的な宇宙で安全に暮らすっていうこと』)
・田口俊樹(『ゴーストマン 時限紙幣』、『ベント・ロード』)
・高野優(『三銃士の息子』)
・中川みほ子(『探偵サミュエル・ジョンソン博士』)
・佐藤良明(『重力の虹』)
・柴田元幸(『プリティ・モンスターズ』、『遁走状態』)
どうみても反則だけど、しょうがない。
[ノンフィクション・評論・エッセイ部門]
☆マイケル・ルイス『フラッシュ・ボーイズ 10億分の一秒の男たち』(早川書房)
文字通り光の速度で反則すれすれの取引を行う業者を向こうに回してどう戦うのか? 言ってみれば圧倒的マッスルを備えた巨人に脳みそひとつ、ロジック一発でいかに勝利するかというお話でもあって、とってもエキサイティングなバトルもの。そして、新しい登場人物が出てくるたびに入念なキャラ付けが行われる、これもキャラ小説ですね。
・伊藤彰彦『映画の奈落:北陸代理戦争事件』(国書刊行会)
あるヤクザ映画が本物の抗争を引き起こしてしまった、ヤクザ映画界に名高い「『北陸代理戦争』事件」を完全ルポ。ヤクザにはヤクザの業があり、映画人には映画人の業があり、筆者には筆者の業がある。
・諏訪部順一『ノワール文学講義 - A Study in Black』(研究社)
おもしろくてためになる。
・マルグリット・デュラス『私はなぜ書くのか』(河出書房新社)
映画監督で作家のマルグリット・デュラス、最晩年のインタビュー。当時におけるフランスの大作家や大哲学者の名前がバンバン出てきては片っ端からディスられていき、その注釈ではディスられた相手からのディスり返し(「あの婆ァ劣化したよね」)が打たれる。他人の喧嘩はエンターテイメント、ファイターに知性があればあるほど面白い。喧嘩以外の箇所も彼女の小説とおなじく流れる詩のようで、快楽性があります。
・野崎歓『翻訳教育』(河出書房新社)
よく覚えてないけど、森鴎外と森茉莉のくだりが愉快だった記憶があります。
・架神恭介『仁義なきキリスト教史』(筑摩書房)
新約聖書をヤクザ映画のノリに翻訳するという気持ちはわからないでもないがそれは無理だろというプロジェクトをやらせてみたら、やっぱりところどころ無理をきたしていて、でもそういうのもひっくるめて笑えるのでよかったんじゃないでしょうか。ヤクザ映画文体っていうか仁義なき文体はかなりのコピー精度でした。
[新人&初訳部門]*7
☆ブライアン・エヴンソン(『遁走状態』)
ブライアン・エヴンソンは不安の在処を知っている数少ない作家の一人だとおもいます。
・キジ・ジョンスン(『霧に橋をかける』)
サムシング新しいものが欲しいなら、キジ・ジョンスン。
・ダニエル・フリードマン(『もう年はとれない』)
上手い作家にも色々タイプがあって、なんか全体的に大味というかおおぶりだけど上手い作家、みたいな人っているじゃないですか。それがダニエル・フリードマン。少し残念なクリント・イーストウッドが『マネーボール』のときのジョナ・ヒルとナチスの残党及び隠し資金を探す話です。
・チャールズ・ユウ(『SF的な宇宙で安全に暮らすっていうこと』)
まあ確かに叙情が円城塔と似ているし同一人物説があるのものわかるぜ、チャールズ・ユウ。『プリムローズ・レーンの男』に賛辞を寄せていると聞くし、実在するんだろうけど。
・伊藤彰彦(『映画の奈落:北陸代理戦争事件』)
伊藤明彦はノンフィクションなのに語りがちょっと小説的というか、晦渋というか、そういう度を超えたシリアスさが題材とマッチしてましたね。
・ローリー・ロイ(『ベント・ロード』)
今年の掘り出し物は『ベント・ロード』。発売三ヶ月で読書メーターの読了数が十六人しかおらんのはどういうことだ。確かに「エドガー賞新人賞!」に何度も騙されてきたってのはわかるけど。ちょっと文体読みやすくなった女性作家版フォークナーって感じですかね。アメリカの嫌な田舎ものが大好きならばマスト。
・ロジャー・ホッブス(『ゴーストマン 時限紙幣』)
『ゴーストマン』、今年を代表するクライム・フィクションかといえばそれはどーかなと一歩下がっちゃう感じですが、細部に特化したフェティシュな文体から漂うどうしたって隠せないオスっぽさには抗えない。
[単発漫画]
☆田中雄一『田中雄一作品集 まちあわせ』
「構成が抜群に上手い。オーソドックスから語り始めて、最後にそこから一歩前にはみ出した感触がある」
・山本美希『ハウ・アー・ユー?』
「ハードコアな理屈で突き詰められた端正な才能」
・高野文子『ドミトリーともきんす』
「一コマ一コマが祝福に満ちている」
・吉元ますめ『イモムシのおよめさん』
「異種婚姻譚界のフロントランナーにして孤高の走者の第一短篇集。死んだと思ったら生きていた」
・鶴田謙二『ポム・プリゾニエール』
「ツルケン美女が意味もなく全裸でイタリアを歩いてさらくだけの漫画。某氏をして『この世にでてはいけない本』『関わった人間が全員正気を失っていた』と言わしめた呪われしクールジャパンの極北」
・高山和雅『天国の魚(パラダイス・フィッシュ)』
「オールド・スクールなガジェットを一分の隙なく並べた芸術的なSF漫画。初稿から15年経ってようやく一般受けする下地が整ったか」
・宮崎夏次系『夢から覚めたあの子とはきっと上手く喋れない』
「三年連続三回目のノミネート」
・村山慶『きのこ人間の結婚』
「漫画ではないにも関わらずさも漫画のようなツラで漫画として出版されることに奇跡を感じる」
・panpanya『蟹に誘われて』
「幻想のなかに滲む人間の辛さに磨きがかかっている」
・吉富昭仁『ゆめにっき』
「ゆめにっきやったことないけど、ちゃんと吉富昭仁になってる」
・辰巳ヨシヒロ『辰巳ヨシヒロ傑作選』
「もっと読もう、辰巳ヨシヒロ」
[海外コミック・BD]
☆『かわいい闇』(河出書房新社)
「みんな気軽に組み合わせる「かわいい」と「ダーク」だけど、この作品ほど高度にバランスがとれたものは稀有」
・『シン・シティ1』(小学館プロダクション)
「フランク・ミラー。もちろん、一ページめくるごとに『かっけえ』と溜息が漏れる」
・『アストロシティ: ライフ・イン・ザ・ビッグシティ』(ヴィレッジブックス)
「ヒーロー世界に済む人々の日常のお話。ハイ・コンセプトな出落ちに堕していない」
・『ミラクルマン Book One: ドリーム・オブ・フライング』(ヴィレッジブックス)
「『ウォッチメン』の元ネタと言われる幻の作品。アラン・ムーアは未完でも完成している」
・『ビフォア・ウォッチメン:ミニッツメン/シルク・スペクター』(ヴィレッジブックス)
「ビフォア・ウォッチメンはどれも好きだけど、どれか一つとなると、やはり『ミニッツメン』」
・『HITMAN 2』(エンターブレイン)
「水族館の海物たちがゾンビになる」
・『キック・アス2』&『ヒット・ガール』
「映画の七百倍酷くて面白い」
・『マイ・リトル・ポニー:ポニーテールズ』
「非常にクオリティの高いアニメコミカライズ」
・『Seconds』(Ballantine Books)
「ブライアン・リー・オマリーの怪奇恋愛リセットSF。『スコピル』ではまだ不安定だったBLOのポップな画風がついに完成し、縦横なイメージを描く」
[映画脚色]*8
☆ギリアン・フリン『ゴーン・ガール』(ギリアン・フリン『ゴーン・ガール』)
・アンドリュー・ボーウェル『誰よりも狙われた男』(ジョン・ル・カレ『誰よりも狙われた男』)
・アンドラーシュ・セーケル&ヤーノシュ・サース『悪童日記』(アゴタ・クリストフ)
・ハビエル・グヨン『複製された男』(ジョゼ・サラマーゴ『複製された男』)
・高田亮『そこのみにて光輝く』(佐藤泰志『そこのみにて光輝く』)
『悪童日記』も『誰よりも狙われた男』もよくもまあまとまったなあ、という感想なんですが、まとまりのよさでは『ゴーン・ガール』の右に出るホンはないでしょう。文庫にして上下巻の小説を二時間の映画脚本としてアダプテーションするときに何を削るって何を足すか、その判断がいちいち的確で、おなじプロットながらもまた別の完成された魅力をもたらしてくれました。
『複製された男』は才に走りすぎた印象。あれはあれで好き、といえば『TOKYO TRIBE』もそうなんですけれどね。
つかれた。
