注意:本記事は新海誠『天気の子』の重大なネタバレを含みます。
(『天気の子』、weathering with you、新海誠監督、日本、2019年)
彼はその海岸で、ひとにぎりの砂をすくう。それが「世界」だ。もちろんそれが現実に広大さをたずさえた世界であるはずがないことは、だれでも知っている。だがそれでもなお、そのひとにぎりの世界について、局地的に、個人的に、沈黙への誘惑にさからって、熱心に語らなくてはならない。
――管啓次郎『狼が連れだって走る月』河出文庫
映画は少年によるモノローグから始まる。
本来なら彼が知らないはずの少女の体験を神の視点から克明に描写する。全知であるかのようにふるまう。
にもかかわらず、観客の前に登場した少年はなにも知らない。
仕事の捜し方も、都会での生き延び方も、林立する看板やブランドの読み方も、そこに生きる人々も、世界の秘密も、故郷で感じた息苦しさの解消法も知らない。
そうして、少年にとって触れ得ないものはすべて「東京」に集約される。東京はその本性を徹底的に隠す。そしてその不可解さは少年にとって自分より先にあるものとして映る。
主人公・帆高が東京で出会うひとびとはみな彼よりおとなだ。彼と同じく十代で家出し、東京でタフな自営業者として生き抜いてきた須賀。高校生の帆高にとって仕事上の先輩であると同時に、ワンステージもツーステージも上の段階にある就活に勤しむ夏美。十七才(「あと一ヶ月で十八才」)と帆高より少し年上で、小学生の弟・凪との二人暮らし生活をひとりで支える陽菜。帆高たちを監視、追跡する警察。風物の由緒に詳しいおばあさん。その孫の神木隆之介。指輪選びのアドバイスをくれるどこかで見た女。
なんとなれば、帆高より年下であるはずの凪ですら恋愛や物事の達観具合において帆高より先を行っている。なにせ、ファーストコンタクトにおいてプレイボーイっぷりを見せつける凪に対して抱いた感想は「東京の小学生って進んでるなあ*1」だ。凪もまた、不可思議のヴェールに覆われた東京の一部として帆高に理解される。
そう、彼は東京を知らない。東京行きの船内でのビールの値段も、高校生が学生証なしでできるバイトも、都会でありうべき金銭感覚*2も、須賀と夏美の関係も、夏美の抱える苦悩も、陽菜の本当の年齢も*3、陽菜の祈りの対価も、東京に属する事柄はほとんどひとつも知らない。
帆高にとって迷ったときに頼れる相手は(須賀や陽菜と出会ったあとでさえ)ヤフー知恵袋=インターネットであるのだけれど、しかしネットは有意な答えを返してくれない。世界は彼の相手をしている暇などないか、あるいは彼の求めている個人的な答えなど知らない。ここからネットは決してパーソナルな友人にはなってくれないという監督の思想性を読み取ることもできるけれど、今回は深入りするのはやめよう。
なぜなら今の世界は、ランタイム二時間のあいだの世界は「東京」とイコールになっている。
陽菜は初めて自分の家に帆高を迎えたとき、こう尋ねる。「東京に来て、どう?」
帆高は返す。「そういえば――もう(故郷で感じたような)息苦しくは、ない」。
すると彼女は「そ、なーんか嬉しっ」と微笑む。
このやりとりから読み取れるのは、帆高が東京にとって客人であるということだ。よそから来た人間が自分の住んでいる土地にやすらぎを見出すのは、土地の人間にとっては「嬉しい」。裏を返せば帆高は陽菜と違って東京の一部ではない。陽菜と帆高は他人である。*4
と、同時に帆高がふるさとでの息苦しさから脱して呼吸の仕方を覚えたのは、須賀のもとで取材に駆け回ることで東京の貌を知り、陽菜とも出会ったことで、彼もまた東京の一部として根を張りはじめたことの証左でもある。
以後、陽菜を知ることと東京(=世界)を知ることは連動していく。
晴れ女稼業を開始することで経済的にも自立*5し、晴れ間という新しい光が射すことで、ますます東京の景色が広がっていく。帆高自身の心もまた、神宮外苑花火大会での浴衣姿といった新しい陽菜の貌によって広がっていき、恋という感情に発展する。
やがて、陽菜の力の秘密の一端に触れるまでになる。
だが、核心の部分で帆高はまだ東京ではない。彼は陽菜の秘密のすべて――つまり、祈りが彼女の身体におよぼす影響を知らされてはいない。
では、いつ帆高は東京になるのか。
警察*6に追われるようにしてアパートから退去する準備をしながら、陽菜は帆高に「補導される前に実家へ戻ったほうがいい」と勧め、こう告げる。
「私たちは、大丈夫だから」
この「私たち」とは陽菜と凪のみを指す。帆高は含まれていない。疑似家族的な関係を結びつつも、ギリギリのところで家族としては認められてはいなかった。
帆高はしょせん東京の外に帰るべき家をもつ客人なのだ。そこに陽菜は線を引く。日常的に使われる「大丈夫」には場合に応じてさまざまな意味が込められるけれど、このときの「大丈夫」は帆高を切り離して守るやさしさとしての「大丈夫」だ。*7
だが、帆高はその「大丈夫」を拒絶する。
「俺、帰らないよ。一緒に逃げよう!」
それは陽菜といっしょに東京を生きることの宣言でもある。
帆高の東京化は一段階上のステージへと移行し、より高度の秘密へのアクセス権を得る。
そうしてなんやかんやがあり、最終的に彼は陽菜の秘密=東京の秘密=世界の秘密を手に入れるわけだ。
もはや少年は無知ではない。逆に、世界の知らない秘密を自分たちが握るという立場になる。かつて東京の秘密を帆高から隠していた須賀や警察といったおとなたちは、逆転したあとの東京ではむしろ「知らない」ひとたちとして扱われる。
ふたりだけの秘密。それは東京を滅ぼす秘密でもある。それは「僕たちは世界の形を決定的に変えてしまった」というフレーズで表現される。それは確信をもって描かれる。
が、その確信はいったん、カッコでくくられる。
東京になったはずの帆高は陽菜と引き離され、故郷の島へと戻される。そこで三年を過ごす。彼は大学入学を機にふたたび上京する。
三年後の東京はすっかり海に沈んでいる。
再会したおとなたちは「東京はもとの姿に戻っただけ」「おまえたちが世界の形を変えてしまったなんて、あるわけない」という。*8
陽菜と帆高が体験し、ふたりをつないだ秘密は幻想だったのだろうか。ふたたび東京はおとなたちの手に戻ってしまったのだろうか。
想いがゆらぎ、三年前のように東京と切り離されそうになる。が、陽菜と再会すると、彼はかつて得た確信を取り戻す。
感極まって号泣する帆高は陽菜*9から「大丈夫?」と訊かれ、こう応える。
「陽菜さん、僕たち、僕たちは大丈夫だ」
これが映画のしめくくりとなるセリフだ。
逃避行直前の「私たちは大丈夫だから」の指す範囲はここで裏返る。今回の「私たち」には帆高も含まれる。東京の秘密を引き受け、雨に濡れることを、世界の変容を受け入れた先に、ようやく「僕たち」としての東京で生きることができる。
知っているからこそ「大丈夫」ということばを吐ける。
「世界が君の小さな肩に乗っているのが僕だけには見えて」いるからこそ「君にとっての『大丈夫』にな」りうる。*10
おたがいにとっての「大丈夫」になれるのは、おたがいしかいない。なぜなら、世界の秘密を真に握っているのは帆高と陽菜のふたりだけなのだから。
ここに至り、ようやく線は引き直される。
ふたりは東京になる。

- アーティスト: RADWIMPS
- 出版社/メーカー: UNIVERSAL MUSIC LLC
- 発売日: 2019/07/19
- メディア: MP3 ダウンロード
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 新海誠
- 出版社/メーカー: KADOKAWA
- 発売日: 2019/07/18
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログを見る
*1:「怖ぇ〜」だったかもしれない
*2:「特売で買えっていったでしょ!」、「五千円は高すぎるかな?」
*3:と同時に彼女がバイト先を首になった理由も
*4:他者性を土地に求めるのはいろんな意味で新海誠らしい見方だ
*5:といっても携帯の費用や家賃はまだ須賀もちなわけですが
*6:来京当初から執拗に帆高を東京から排除しようとする存在として描かれている彼らが、帆高にとっては致命的な陽奈の秘密、すなわちほんとうの年齢を握り、かつ彼にそれを報せる役割を与えられている事実のはきわめて重要です。脚本のいじがわるい。
*7:陽菜たちは東京の一部でありながらも、東京に押しつぶされていきもする両義的な存在だ。東京の歪みを引き受けているといってもいい。彼女は人柱なのだから。その点においては彼女は東京外の人間である帆高を巻き込むわけにはいかなかった
*8:セカイ系というよばれる作品群についてはあまり真剣に向き合ったことがないのだけれど、『イリヤの空』を読んだ記憶から導き出される自分なりの要件は「良きにつけ悪しきにつけ、おとながなんだかんだで世界の全容を把握し、それに対する責任を引き受けていること」になるんだと思います。しかしまあこの二十年でおとなが世界を責任持って把握しハンドリングしているというのは嘘っぱちなんだと小学生でも知るようになってしまった。あとは細分化された体験のみが真実な世界です
*9:陽菜も泣いている
*10:エンディングのRADWIMPS「大丈夫」の歌詞から。ラストのセリフはこの歌から導き出されたものだという(『小説版 天気の子』あとがき)』







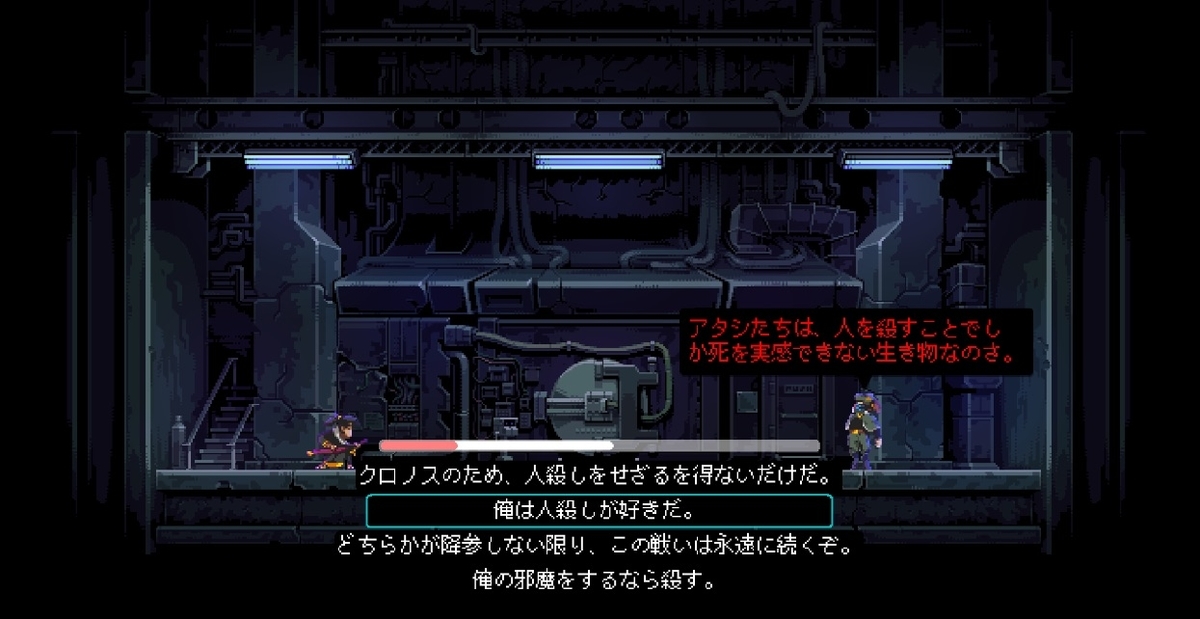
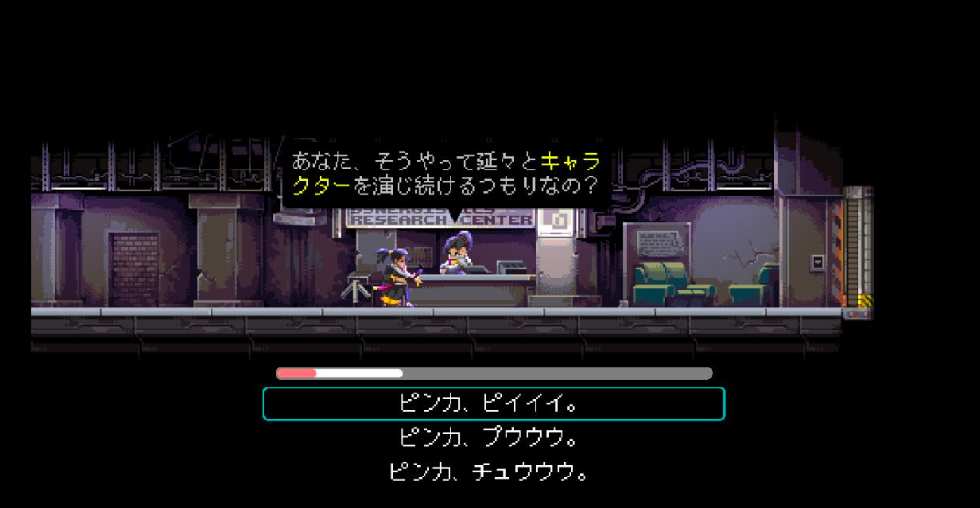
![アドベンチャー・タイム シーズン5 Vol.2 [DVD] アドベンチャー・タイム シーズン5 Vol.2 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/61KzdK+T-9L._SL500_.jpg)